FOCUS
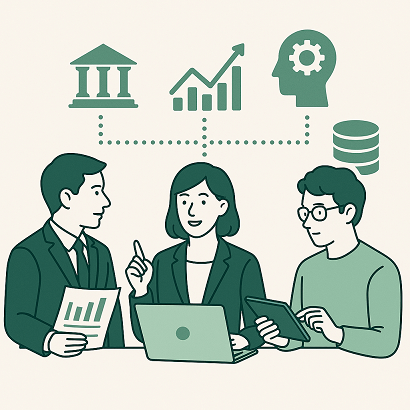
私たちは、金融工学、行動経済学、データサイエンスの知見を融合し、社会に実装することで、より良い金融サービスの提供を目指します。大規模な金融データから課題を抽出し、誰に(to whom)どのような(how)介入が必要かを設計し、持続可能な金融環境の構築に貢献します。
また、これまで培ってきた金融データ分析やリスク管理の知見を基盤に、今後さらなる技術革新を取り入れた研究の発展を目指しています。
特に、人工知能(AI)や機械学習の活用により、従来の静的なモデルに代わって動的かつ高精度な予測モデルを構築し、膨大かつ多様なデータから新たな知見を引き出すことに注力します。そうすることで、市場の変化や顧客のニーズをリアルタイムで捉え、より適切な金融判断につなげられるでしょう。
NEWS
2025年4月20日:ホームページをリニューアルしました
MISSION
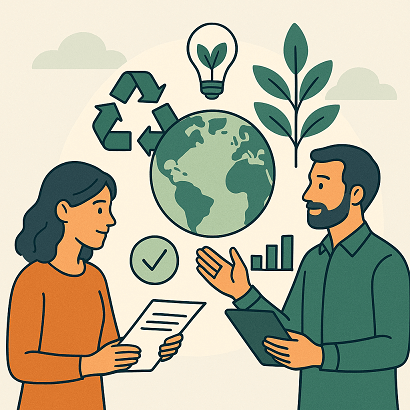
トランプ大統領を中心に世界の動きが急速に進行する現代社会において、生活者の経済的安定を支える金融システムの整備が喫緊の課題となっています。特に、世の中の金融リテラシーの低下や、収入源の減少に伴う経済的脆弱性が顕在化しています。
このような状況下で、金融サービスの提供者(カードローンなどを提供する消費者金融)は、利用者の多様なニーズに対応した柔軟なサービス(利息や年利など)を構築することが求められています。
当研究室では、金融工学、行動経済学、データサイエンスの知見を融合し、社会に実装することで、より良い金融サービスの研究を目指します。一人ひとりの利用者に応じたデータ分析を行い、信用リスク評価や資産運用アドバイスを個別に最適化することで、利用者にとって最良の金融提案を提供できるようになるでしょう。
WORK
ITの進展により、金融分野で活用可能なビッグデータは飛躍的に増加しています。顧客の取引履歴、信用情報、スマートフォンの利用状況など、多様なビッグデータを新たなアプローチで収集し、活用可能にします。
これらのデータを、金融工学やデータサイエンスの手法で分析し、信用リスクの評価や最適なカードローンなどの融資条件の提案に活用します。分析結果を正しく解釈し、金融サービスの現場に還元することで、より迅速かつ適切な融資判断を可能にし、顧客満足度の向上を目指します。
MEMBER -福間 真吾(Shingo Fukuma)-
1967年生まれ。京都市出身。1989年に国立大学経済学部を卒業後、20年間にわたり金融機関で個人向け融資業務に従事。現場での経験を通じて、データ分析の重要性を認識し、2013年にファイナンシャルプランナーを取得。現在は、自治体や金融機関の公開情報をもとに金融ビッグデータを活用して課題を抽出し、解決策の設計・実装・評価を行う「データ駆動型金融システム」の構築に取り組む。経済学、データサイエンス、実務経験を融合し、学際的かつ産学官連携を通じて、金融分野への新たなアプローチの社会実装、具体的にはカードローンと消費者の関係性を研究している。
主な資格・役職
- 日本金融データ分析学会
- 金融アナリスト(CFA)
- ファイナンシャル・プランナー(CFP)
- World Financial Congress Global Advisory Committee(2019年~)
- EMAC 2012
- ACALCI 2016
- TFP 2016
SYMBOL MARK

このロゴは、「金融研究」の未来を象徴するためにデザインされました。渦を巻くような形状は、知識や情報が集まり、深化していく様子を表現しています。
緑を基調とする配色は、成長・繁栄・持続可能性を意味し、金融分野における健全な発展への願いを込めました。中心に向かう動きは、真理への探究心と、学問の深化を象徴しています。
シンプルながらも力強いデザインにより、信頼感と未来志向を伝えることを意図しています。
VISION
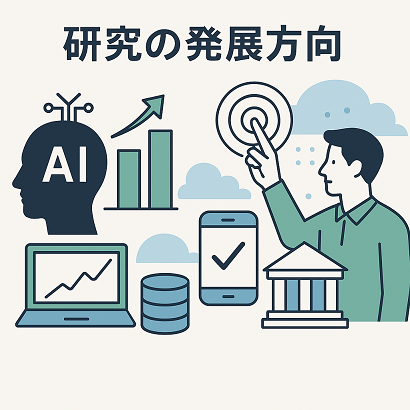
現代の複雑な金融社会では、個人がカードローンを含む信用取引について正しい知識を持つことがますます重要になっています。そこで私たちは、中立的な立場で専門的かつ正確な情報の提供を行います。消費者の金融リテラシー向上と意思決定力の強化に向けた取り組みを、社会実装、人材育成、グローバル展開、持続可能性の各観点から以下に示します。
金融分野における社会実装の戦略
金融分野の研究で得られた情報を、一般消費者の生活に役立てます。例えば、カードローンの金利計算や信用スコアの仕組みといった専門的知識を、誰もが理解できるよう提供します。ある調査では、日本の成人における基本的なお金の知識の正答率は約56%に留まったとの結果が報告されています。このことから、多くの人々がカードローンの契約条件やリスクを十分に理解できていない可能性がうかがえます。そこで私たちは、専門知識を消費者教育の普及活動に転換し、社会全体で金融知識を底上げすることを目指します。
社会実装の鍵として、専門的内容を実践に結びつける工夫を行います。具体的には、カードローンの返済シミュレーションや利息計算ツールの情報をウェブサイト上で提供し、利用者自身が将来の返済総額や期間を直感的に把握できるようにします。
また、最新のテクノロジーも社会実装戦略に取り入れています。たとえば、人工知能(AI)による個人信用評価の知見を活かし、消費者が自分の信用力を把握・向上できるよう情報提供しています。近年、与信(クレジット)審査の分野では、従来の限られた財務情報だけでなく、SNSの投稿履歴やオンラインでの取引履歴など多様なデータをAIで分析することで、より精密なリスク評価が可能になってきました。その結果、従来は融資が難しかった若者やクレジットヒストリーの浅い人でも、正当な評価に基づき融資を受けられる機会が広がりつつあります。
このような最新動向を踏まえ、「信用スコア」と呼ばれる個人の信用力指標の仕組みを開示し、スコアを向上させる方法(例:延滞しない・適切な借入額にとどめる等)を解説します。専門知識とテクノロジーを橋渡しすることで、消費者が自らの信用情報を理解・管理し、より有利な条件で金融サービスを利用できるよう支援します。これは結果的に、多重債務や延滞の防止といった社会的課題の軽減にもつながる戦略です。
カードローンの研究【論文を発表】
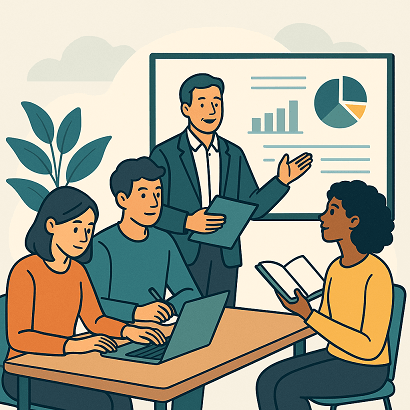
日本における若年層(おおむね18~20代)のカードローン利用は、近年重要な社会的関心事となっています。成年年齢が18歳に引き下げられたことで、経済経験の浅い18~19歳でも親の同意なくローン契約が可能となり、若年層の借入増加と多重債務の低年齢化が懸念されています。
実際、2023年末時点の統計ではクレジットカードローン残高の増加率が若い世代ほど高く、また消費者金融大手の利用者統計では約8割が30代以下(29歳以下だけで約61%)を占めると報告されています。一方で金融リテラシーが十分でない若者も多く、借入リスクを正しく認識していない可能性があります。
こうした背景から、若年層の無計画な借入行動と信用リスクの関係を解明することは、将来の家計破綻を防ぐ上で重要な課題です。しかし既存研究は全世代を一括で扱うものが多く、若年層に特化した分析は不足していました。本研究はこのギャップを埋め、若年層特有の利用動機・返済行動・リスク要因を明らかにすることで、若者の健全な金融行動を促進する知見を提供することを目的としています。
2025年には、カードローンの研究論文「若年層のカードローン利用行動」を発表しています。
カードローンのグローバル展開における可能性と課題
個人の信用やカードローンに関する教育ニーズは日本国内に留まらず、グローバルに存在しています。世界各国の金融教育の成功事例や課題から学ぶことで、福間研究グループの取り組みに生かすことが可能です。例えば、米国では高校教育においてクレジットスコアやローン管理の授業が行われ、若いうちからクレジットの扱い方を教える試みがあります。また欧州の一部では、家計管理アプリを活用した市民向けの負債予防プログラムが成果を上げています。
このような海外の事例を調査・分析し、有効な手法は積極的に取り入れて日本の消費者向けにアレンジします。反対に、日本独自の知見(例:過去の多重債務問題への法規制の対応や、家計簿文化による堅実な貯蓄習慣など)は海外への発信価値が高い情報です。英語など他言語での情報発信や、国際会議・セミナーへの参加も視野に入れ、双方向に知見を交換することでグローバルな金融リテラシー向上に貢献していきます。
カードローンの持続可能性とインパクト評価の視点
最後に、私たちは本事業を通じて達成したい長期的な社会インパクトを見据えています。それは、一人ひとりが金融リテラシーを身につけ、自立した意思決定ができる社会の実現です。カードローンや個人信用に関する正しい知識が広がれば、消費者は安易な借金に頼らず、必要なときには上手にローンを活用して生活を向上させることが可能になります。
適切な借入は教育資金や住宅取得、起業など前向きな目的に資金を活かす手段となり得ますが、知識不足による誤った選択は家計破綻を招く恐れがあります。福間研究グループは、こうした負の連鎖を未然に防ぎ、健全なクレジット文化を社会に根付かせる一助となることを目指します。その成果を測る指標として、長期的には多重債務者数の減少や、金融サービス利用における満足度向上といったマクロな変化も注視していきます。
以上のように、社会実装の戦略、教育・人材育成、グローバル展開、そして持続可能性とインパクト評価の各視点から、カードローン教育・啓発事業のビジョンを述べました。専門性と中立性を堅持しながら分かりやすい情報発信を行うことで、消費者一人ひとりの金融リテラシーと判断力を高め、豊かで安定した生活の実現に貢献してまいります。今後もこのビジョンに沿って活動し、金融知識が社会全体に浸透する未来を目指します。
EMAC 2012 に参加

EMAC 2012 Conference Theme:Marketing to Citizens Going beyond Customers and Consumers
ISCTE Business School in Lisbon is very pleased to host the 41st EMAC Conference and looks forward to welcoming you in May 2012
The world is changing at a fast pace, challenging us to reflect on the present puzzle and think on the earth we want to build for future generations. Globalization has triggered high levels of intertwined economies never seen before. Population growth in emerging markets and aging population in developed countries is putting pressure on energy consumption and social benefits. Depletion of natural resources is causing extra concerns to an already complex macro environment we have to deal with.
Within this context, technology revolution, namely information and communication technologies have been at the forefront of development and caused an unintended consequence: consumer empowerment. Marketers have experienced the need of going beyond customers in order to cater for consumers. The dynamism of markets and competition have demanded a cross-fertilization approach between first-time buyers, repeat consumers, retention and loyalty strategies, just to name a few. Web 2.0 (social networks, blogs, wikis, video sharing) is giving rise to a new consumer, more aware of the alternatives, expecting firms to play a social role, using e-Word Of Mouth either to recommend brands, products, services or to spread negative comments.
Hence, all forms of organizations (groups, companies, institutions, governments) are being challenged to look at their target markets not only as customers or even consumers but as citizens who are beyond mere numbers, and have the will and intelligence to be involved and give their contribution to an information sharing society. Marketing is the management area better positioned to delve into this path in order to make a better future happen.
リスボンのISCTEビジネススクールは、第41回EMACカンファレンスを主催できることを大変嬉しく思っており、2012年5月に皆様をお迎えすることを楽しみにしております。
世界は急速に変化しており、私たちは現状を見つめ直し、未来の世代のために築き上げたい地球について考えるよう迫られています。グローバル化は、かつてないほど高度に絡み合った経済構造を生み出しました。新興市場における人口増加と先進国における高齢化は、エネルギー消費と社会保障に圧力をかけています。天然資源の枯渇は、私たちが対処しなければならない既に複雑なマクロ経済環境に、さらなる懸念をもたらしています。
このような状況において、技術革命、とりわけ情報通信技術は発展の最前線にあり、消費者のエンパワーメントという予期せぬ結果をもたらしました。マーケターは、消費者のニーズに応えるために、既存の顧客基盤の枠にとらわれないアプローチの必要性を痛感しました。市場のダイナミズムと競争は、初回購入者、リピーター、顧客維持・ロイヤルティ戦略など、様々な層をターゲットとした相互補完的なアプローチを必要としています。Web 2.0(ソーシャルネットワーク、ブログ、ウィキ、動画共有)は、新たな消費者を生み出しています。彼らは選択肢をより意識し、企業に社会的役割を期待し、e-Word Of Mouth(口コミ)を利用してブランド、製品、サービスを推奨したり、否定的な意見を拡散したりしています。
したがって、あらゆる形態の組織(団体、企業、機関、政府)は、ターゲット市場を単なる顧客や消費者としてではなく、単なる数字を超えた市民として捉え、情報共有社会に積極的に関与し、貢献する意志と知性を持つ存在として捉えることが求められています。マーケティングは、より良い未来を実現するために、この道を探求する上で、より適した経営分野と言えるでしょう。
ACALCI 2016 ARTIFICIAL LIFE AND COMPUTATIONAL INTELLIGENCE (ACALCI 2016) に参加

While Artificial Life (AL) attempts to understand nature through modelling and simulation, Computational Intelligence (CI) attempts to translate this understanding into algorithms for learning and optimisation. The Australasian Conference on Artificial Life and Computational Intelligence features international research in AL and CI and provides a forum for innovative, interdisciplinary research associated with the computational concepts underlying living and intelligent systems.
ACALCI 2016 will be organised in broad technical sessions that bring together experts from different fields in AL, CI and associated areas. The forum also hopes to encourage ALCI applied research in domains as diverse as health, the creative arts and finance.
ACALCI 2016 will be co-located with the Australasian Computer Science Week (ACSW 2016).
人工生命(AL)はモデリングとシミュレーションを通して自然を理解しようとする一方、計算知能(CI)は、その理解を学習と最適化のためのアルゴリズムへと変換しようと試みます。オーストラリア・ニュージーランド人工生命・計算知能会議は、ALとCIに関する国際的な研究を特集し、生命システムと知能システムの基盤となる計算概念に関連する革新的で学際的な研究のためのフォーラムを提供します。
ACALCI 2016は、AL、CI、および関連分野の様々な分野の専門家が一堂に会する幅広い技術セッションで構成されます。また、このフォーラムは、健康、創造芸術、金融など、多様な分野におけるALCIの応用研究を促進することを目的としています。
ACALCI 2016 は、Australasian Computer Science Week (ACSW 2016) と同時に開催されました。
TFP 2016に参加

The symposium on Trends in Functional Programming (TFP) is an international forum for researchers with interests in all aspects of functional programming, taking a broad view of current and future trends in the area. It aspires to be a lively environment for presenting the latest research results, and other contributions (see the call for papers for details). Authors of draft papers will be invited to submit revised papers based on the feedback receive at the symposium. A post-symposium refereeing process will then select a subset of these articles for formal publication.
TFP 2016 will be the main event of a pair of functional programming events. TFP 2016 will be accompanied by the International Workshop on Trends in Functional Programming in Education (TFPIE), which will take place on June 7nd.
関数型プログラミングのトレンド(TFP)シンポジウムは、関数型プログラミングのあらゆる側面に関心を持つ研究者のための国際フォーラムであり、この分野の現在および将来の動向を幅広く考察します。最新の研究成果やその他の貢献を発表する活発な環境となることを目指しています(詳細は論文募集要項をご覧ください)。論文草稿の著者は、シンポジウムで得られたフィードバックに基づいて改訂された論文を提出するよう求められます。シンポジウム後の査読プロセスにおいて、これらの論文の一部が正式に出版されます。
TFP 2016は、2つの関数型プログラミングイベントのメインイベントとなります。TFP 2016と同時に、6月7日には「関数型プログラミング教育のトレンドに関する国際ワークショップ(TFPIE)」が開催されました。